透きとほるほどの白き指ものいはばいかなる声か聞きたしわれは
指の歌といえば、塚本邦雄の「晴天にもつるるとほきラガー見む翳(かざ)せいゆびの間(あひ)の疑獄に」(『緑色研究』)がすぐ思い浮かぶ。指の間から垣間見る地獄。青春とは地獄なのだとむかし勝手に理解し愛誦していたが、もつるる「快楽」だと後に思い知った。指の歌は官能的な作が多い。斎藤茂吉の「しんしんと雪ふりし夜にその指のあな冷たよと言ひて寄りしか」(『赤光』)とか佐佐木幸綱の「わが夏の髪に鋼(はがね)の香がたつと指からめつつ女(ひと)は言うなり」(『夏の鏡』)など。これらの名作のあとに気引けるが、早稻田短歌時代に「においたつほそくましろい花びらがまひるおんなの指となりゆく」の歌を発表したことがある。さすがに歌集には収めなかった。
作者/伊藤一彦(いとうかずひこ)

1943年、宮崎市生まれ。「心の花」会員。「現代短歌 南の会」代表。若山牧水記念文学館長。読売文学賞、寺山修司短歌賞、迢空賞、斎藤茂吉短歌文学賞など受賞多数。
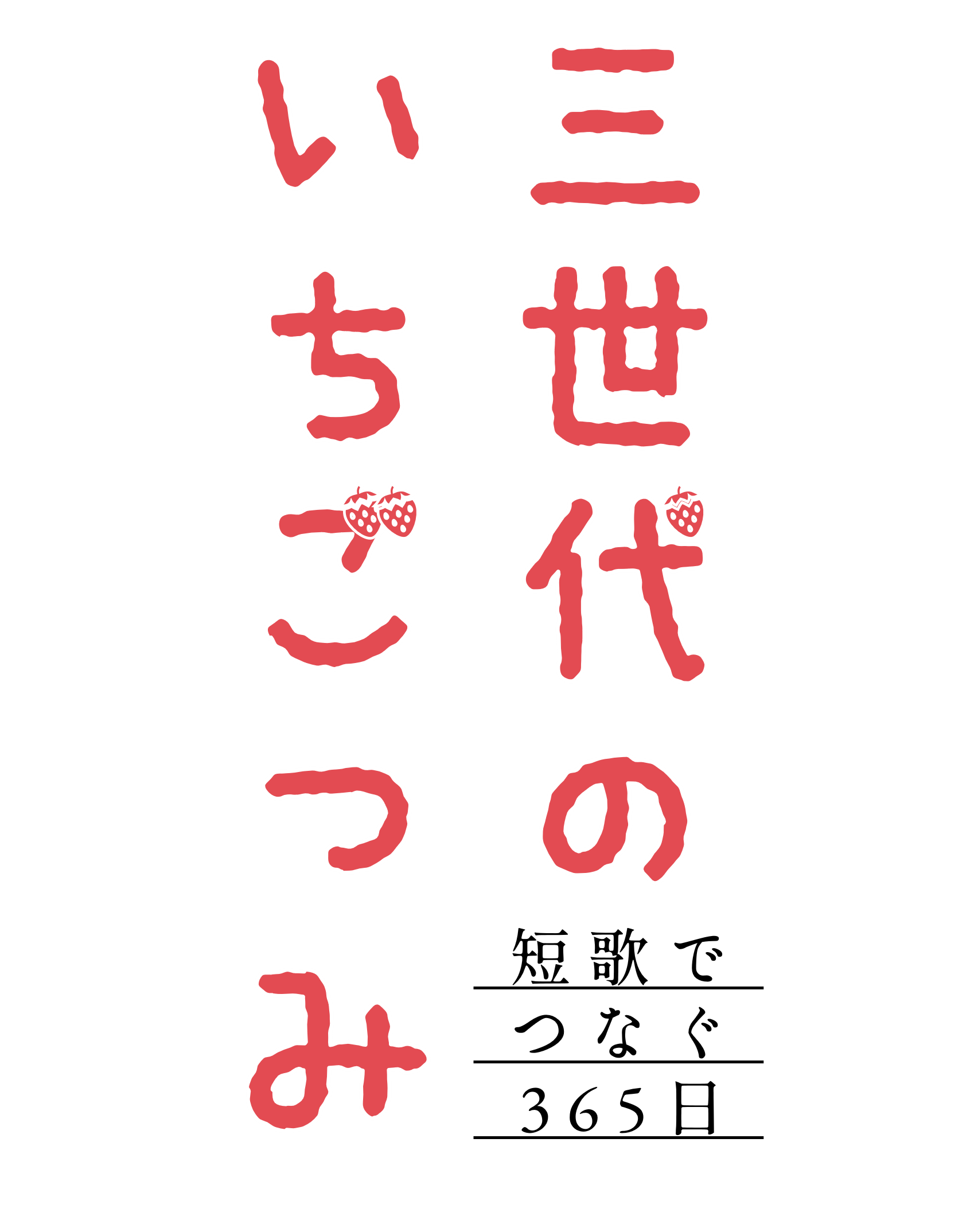

コメント