「はふはふ」と「ばぶばぶ」とまた「ぱぷぱぷ」とハ行は楽しことに半濁は
五十音図の横の並びの「カサタナハマヤラワ」はどんな順番でならんでいるか。答えは子音を発音する位置。カ行は口の奥で作り、サ行は口の上の部分に舌を当てて作り、タ行とナ行は歯茎で作りというように、音を作る位置がだんだん前に出てくる。しかし、ハ行だけは例外。口の奥で出す音でカ行に近いのになせ。橋本陽介著『日本語の謎を解く』(新潮社)という私の愛読書が教えてくれる。五十音図が作られた平安時代にはハ行の音はなく、ハ行はかつてパピプペポと発音されていて、それが平安時代にはファ、フィ、フ、フェ、フォとなっていたらしい。パ行もファ行も唇を使う音だからタ行の後ろでよいのだと。ハ行だけに半濁音のある理由がこれでよくわかる。ともあれ、この橋本氏の本は目から鱗ウロコの落ちる話がいろいろ出てくる、私の推し本だ。
作者/伊藤一彦(いとうかずひこ)

1943年、宮崎市生まれ。「心の花」会員。「現代短歌 南の会」代表。若山牧水記念文学館長。読売文学賞、寺山修司短歌賞、迢空賞、斎藤茂吉短歌文学賞など受賞多数。
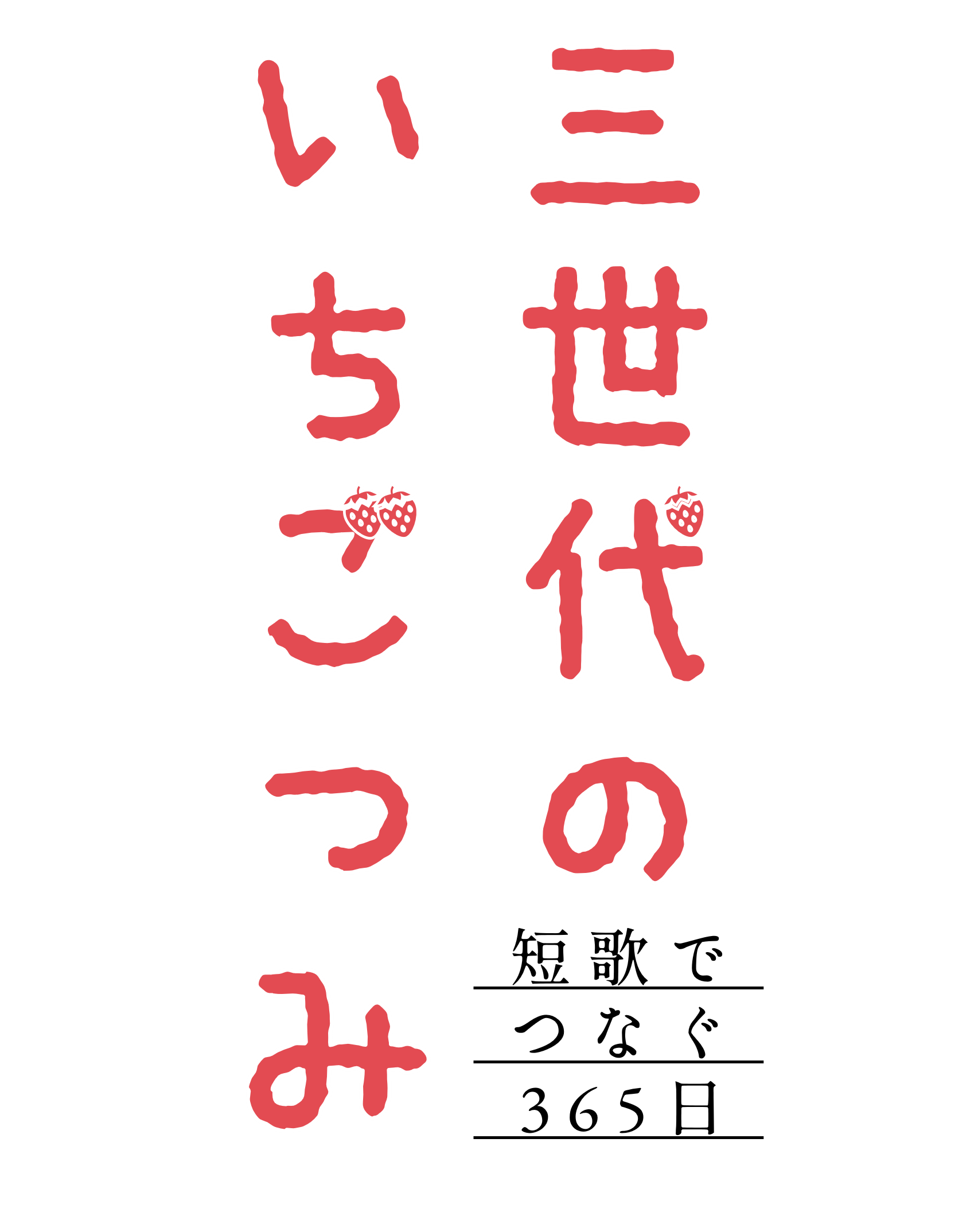

コメント